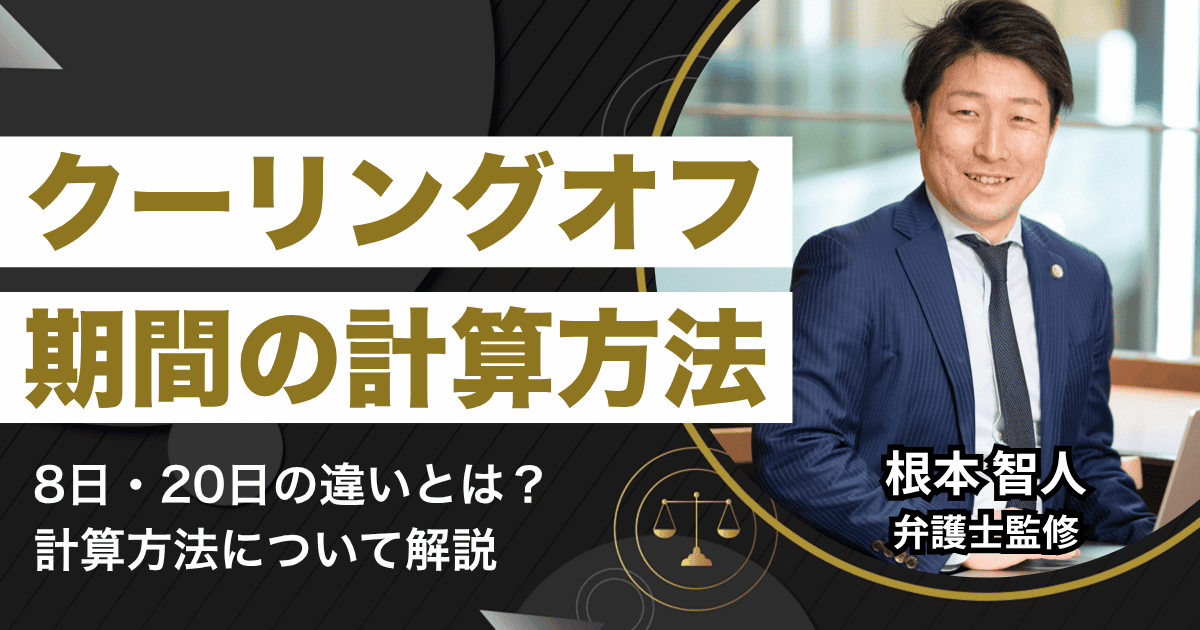「つい契約してしまったけど、やっぱりやめたい…」
訪問販売や電話でのしつこい勧誘に根負けし、高額な契約を結んで後悔している方は少なくありません。「いつまでなら解約できるんだろう?」と、時間が経つにつれて焦りや不安は募るばかりです。
しかし、安心してください。そんな時に消費者を守ってくれるのが「クーリングオフ制度」です。この制度は、一度結んだ契約を一定の期間内であれば無条件で一方的に解除できる、法律で認められた消費者の強力な権利です。
この記事では、クーリングオフについて、以下の点を徹底的に解説します。
- 契約ごとに異なるクーリングオフの期間と正しい計算方法
- はがきやメールでの具体的な手続きとそのまま使える文例
- クーリングオフの対象になる契約、ならない契約
- 期間が過ぎてしまった場合の対処法と相談先
この記事を最後まで読めば、クーリングオフに関する疑問や不安が解消され、ご自身の状況を正確に把握したうえで、冷静かつ確実に行動を起こせるようになります。望まない契約の悩みから解放され、心の平穏を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。
.jpg)
クーリングオフの期間はいつまで?取引別の期間と正しい計算方法
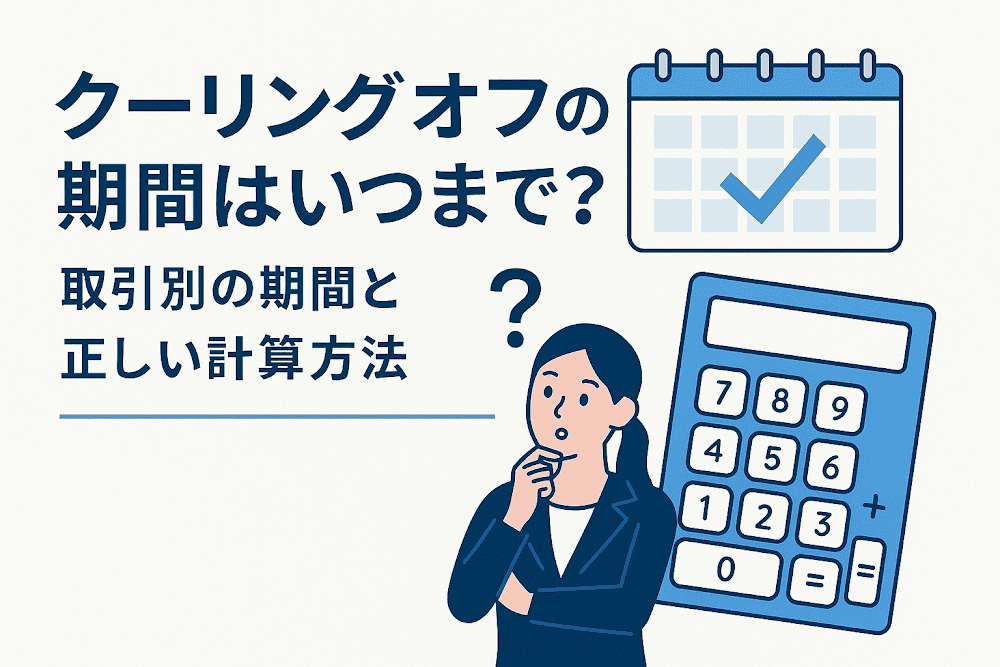
クーリングオフを検討する際、最も重要なのが「期間」です。期間を1日でも過ぎてしまうと、原則としてこの制度は利用できません。
ここでは、契約を解除できる正確な期間を把握するために、以下の3つのポイントを解説します。
- 取引別の期間一覧
- 正しい期間の計算方法
- 期間が延長される例外ケース
ご自身の契約と照らし合わせながら、正確なタイムリミットを確認していきましょう。
【一覧表】訪問販売は8日間、マルチ商法は20日間など契約で異なる期間
クーリングオフが可能な期間は、すべての契約で一律ではありません。契約の不意打ち性が高いほど、消費者が冷静に考えるための期間が長く設定されています。
具体的には、特定商取引法などで定められた取引類型によって、期間は以下のように異なります。
| 取引類型 | クーリングオフ期間 | 具体例 |
| 訪問販売 | 8日間 | 自宅への訪問、キャッチセールス、アポイントメントセールス |
| 電話勧誘販売 | 8日間 | 事業者からの電話による勧誘での契約 |
| 特定継続的役務提供 | 8日間 | エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス |
| 訪問購入 | 8日間 | 事業者が消費者の自宅等を訪ねて商品を買い取る契約(押し買い) |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 | 「他の人を勧誘すれば儲かる」といった形で商品・サービスを契約させる取引 |
| 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) | 20日間 | 「仕事を提供するので収入になる」と誘い、商品やサービスを契約させる取引 |
このように、ご自身の契約がどの取引にあたるかによって、期間が8日間なのか20日間なのかが変わってきます。まずは契約書などを確認し、どの取引類型に該当するのかを把握することが第一歩です。
クーリングオフ期間の正しい計算方法|起算日は「契約書面を受け取った日」
クーリングオフ期間のカウント方法は法律で明確に定められており、その起算日(カウントを始める日)の認識が非常に重要です。
期間は、法定の契約書面(申込書面または契約書)を受け取った日を1日目として計算します。契約した日や商品が届いた日ではない点に注意が必要です。例えば、8日間のクーリングオフ期間の場合、以下のようになります。
- 月曜日に契約書面を受け取った場合
- →その日を1日目としてカウント開始
- →期間の最終日は翌週の月曜日
この計算には、土日や祝日も含まれます。期間の最終日の消印有効で通知すればよいため、最終日が日曜日であっても、その日に郵便局の窓口(ゆうゆう窓口など)から発送手続きをすれば間に合います。起算日を間違えて「まだ大丈夫」と思い込んでいると、手遅れになる可能性があるため、正確にカウントしましょう。
契約書面の不備やクーリングオフ妨害があった場合の期間の扱い
もし、すでに期間が過ぎてしまっていても、諦めるのはまだ早いかもしれません。特定の状況下では、クーリングオフ期間が進行しない、あるいは延長されるケースがあります。
その代表的な例が、「契約書面の不備」と「クーリングオフ妨害」です。
事業者が渡すべき契約書面には、クーリングオフに関する事項を赤枠の中に赤字で記載するなど、法律で定められた形式があります。もし、この記載がなかったり、内容が不十分だったりする不備のある書面しか受け取っていない場合、クーリングオフ期間は進行しません。つまり、いつでもクーリングオフが可能になります。
また、事業者が「この契約はクーリングオフできない」「解約するなら違約金を払え」などと嘘を言ったり、威圧的な態度で解約を妨害したりする「クーリングオフ妨害」があった場合も同様です。この場合、事業者が改めてクーリングオフできる旨を記載した書面を交付してから、新たに期間が進行することになります。
期間が過ぎたと思っても、まずは契約書面の内容を隅々まで確認し、事業者の言動を思い出してみることが重要です。
クーリングオフ期間内に行う手続きの全手順|はがきの書き方からメール通知まで
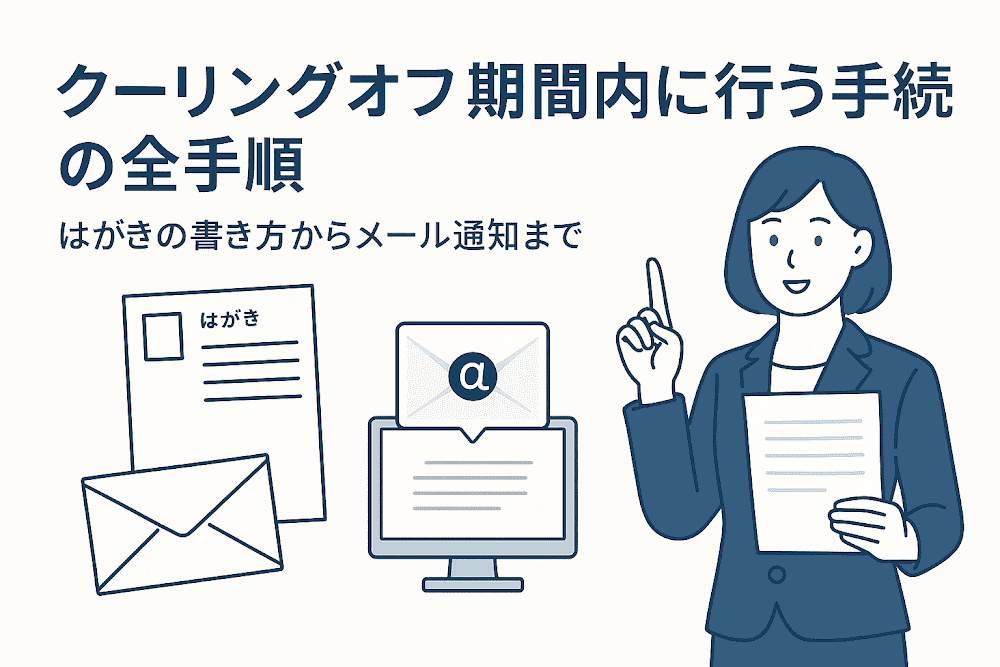
クーリングオフの意思は、必ず書面または電磁的記録(電子メールなど)で通知する必要があります。口頭で伝えただけでは、後から「聞いていない」と言われてしまうトラブルになりかねません。
ここでは、確実に契約を解除するための具体的な手続きを解説します。
- 最も確実な通知方法である「内容証明郵便(書面)」での手続き
- 2022年から可能になった「メール」での手続き
どちらの方法でも法的な効力は同じですが、それぞれに注意点があります。
最も確実な通知方法|内容証明郵便(書面)の書き方と送付の注意点
内容証明郵便などの書面による通知は、古くからある方法ですが、手元に物的な証拠が残るため、現在でも非常に確実な方法と言えます。
クーリングオフ通知書に記載すべき内容はシンプルです。以下の項目を漏れなく記載しましょう。
- タイトル:「契約解除通知書」など
- 契約年月日
- 商品名・サービス名
- 契約金額
- 販売会社名、担当者名
- 「上記の契約を解除します」という明確な意思表示
- 通知日
- ご自身の住所・氏名
これらの情報を記載し、証拠が残る方法で送付することが、後のトラブルを防ぐ上で極めて重要になります。
【文例付き】そのまま使えるクーリングオフ通知内容証明郵便の記載例
実際に書く際の文例を以下に示します。ご自身の状況に合わせて修正してご活用ください。内容証明郵便によることが難しい場合には、はがき一枚で送付することもできますが、内容証明郵便のように通知された証拠が完全に残るものではありません。少なくとも両面のコピーを必ず取っておき、特定記録郵便又は簡易書留にて送付しましょう。なお、各自治体でも文例を公開していますので、参考にするとよいでしょう。(例:新宿区の通知文例)
<商品購入の契約の場合>
契約解除通知書
契約年月日:令和〇年〇月〇日
商品名:〇〇(例:布団セット)
契約金額:〇〇円
販売会社:株式会社〇〇(担当者:〇〇)
上記の契約を、特定商取引法に基づき解除します。
つきましては、支払い済みの代金〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。
令和〇年〇月〇日
住所:東京都〇〇区〇〇
氏名:〇〇 〇〇 印
クレジットカード払いの場合、信販会社への通知も忘れずに
もし代金をクレジットカードで支払う契約(割賦販売)をしている場合は、販売会社だけでなく、信販会社(クレジットカード会社)にも同様の通知書を送る必要があります。
これを忘れると、商品やサービスの契約は解除されても、クレジットの請求だけが続いてしまう可能性があります。販売会社用と信販会社用の2通を作成し、それぞれに送付しましょう。
証拠が残る「内容証明郵便」、「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付する
クーリングオフは、通知書を発信した時点(郵便局の消印日)で効力が発生します。事業者に到着した日ではありません。この「いつ通知したか」を証明するために、必ず証拠の残る方法で郵送してください。
おすすめなのは「内容証明郵便」です。内容証明郵便によることが難しい場合には、「特定記録郵便」または「簡易書留」にて送付しましょう。
- 内容証明郵便:配達の記録に加え、送付した内容も証明されるが、送付方法が少し難しい。
- 特定記録郵便:配達の記録が残り、料金も比較的安い。
- 簡易書留:引き受けと配達の両方が記録され、万一の際の損害賠償も付く。
普通郵便で送ると、事業者に「受け取っていない」と言われた場合に対抗できません。必ず郵便局の窓口で手続きをし、受け取った受領証は、はがきのコピーと一緒に大切に保管しておきましょう。
2022年から可能になった電磁的記録(メール等)での通知方法と文例
法改正により、2022年6月1日から電子メールや事業者のウェブサイトの問い合わせフォームなど、電磁的記録によるクーリングオフ通知が可能になりました。はがきを準備する手間が省け、より手軽に手続きができるようになった点がメリットです。
メールで通知する場合、以下の内容を記載します。件名は「クーリングオフ通知」など、一目で内容がわかるようにしましょう。
<メールでの通知文例>
件名:契約解除通知(クーリングオフ)
株式会社〇〇 御中
以下の契約を、特定商取引法に基づき解除します。
契約年月日:令和〇年〇月〇日
商品名:〇〇
契約金額:〇〇円
担当者名:〇〇様
つきましては、支払い済みの代金〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。
通知日:令和〇年〇月〇日
住所:東京都〇〇区〇〇
氏名:〇〇 〇〇
この方法で通知する際に最も重要なのは、「通知した証拠」を確実に残すことです。送信したメールは必ず保存し、可能であれば送信画面のスクリーンショットも撮っておきましょう。事業者のフォームから通知した場合は、送信完了画面のスクリーンショットを必ず保存してください。
その契約、クーリングオフできる?期間内でも対象外になるケース
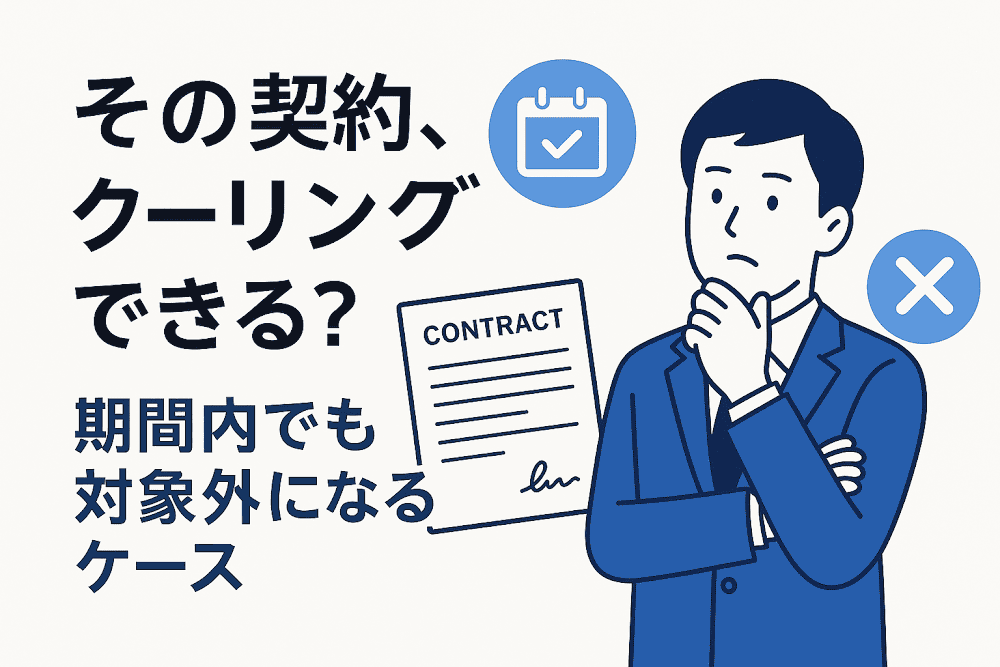
「期間内だから大丈夫」と思っていても、実はすべての契約がクーリングオフの対象になるわけではありません。制度の趣旨から、適用される取引とそうでない取引が法律で定められています。
ここでは、ご自身の契約が対象になるのかを判断するために、以下の点を解説します。
- クーリングオフが適用される主な取引
- 対象外となる代表例「通信販売」
- その他、適用除外となる条件
思い込みで手続きを進める前に、まずは対象になるかしっかりと確認しましょう。
クーリングオフ制度が適用される主な取引類型
クーリングオフ制度は、主に不意打ち性が高く、消費者が冷静に判断する時間を与えられずに契約してしまいがちな取引を対象としています。
具体的には、以下のような取引が法律で定められています。
- 訪問販売:自宅への突然の訪問や、街頭でのキャッチセールスなど。
- 電話勧誘販売:事業者からの電話で勧誘され、契約するもの。
- 特定継続的役務提供:エステや語学教室など、長期間にわたってサービスを受ける契約。
- 連鎖販売取引(マルチ商法):ピラミッド式の組織で、商品を販売したり会員を増やしたりする取引。
- 業務提供誘引販売取引:「在宅ワークで高収入」などと誘い、仕事に必要だとして高額な機材やシステムを契約させる取引。
- 訪問購入:事業者が消費者の自宅を訪れ、貴金属などを強引に買い取っていく「押し買い」。
これらの取引は、消費者が予期せぬ勧誘を受けたり、複雑な契約内容をその場で理解するのが難しかったりするため、後から冷静に見直す期間が与えられているのです。
通信販売はクーリングオフ期間の対象外!「返品特約」を確認
クーリングオフで最も誤解が多いのが「通信販売」です。インターネット通販やテレビショッピング、カタログ通販などで購入した商品は、原則としてクーリングオフ制度の対象外となります。
これは、通信販売が、広告を見て消費者自らの意思で申し込みを行うものであり、訪問販売のような「不意打ち性」がないためです。購入までに情報を比較したり、検討したりする時間があると判断されています。
ただし、クーリングオフができないからといって、一切返品できないわけではありません。通信販売では、事業者が独自に定める「返品特約」が適用されます。サイト上に「商品到着後〇日以内なら返品可能」「お客様都合の返品は不可」といったルールが記載されているはずです。もし、返品に関する記載がどこにもない場合は、商品到着後8日以内であれば送料消費者負担で返品が可能です。購入前に、サイトの隅々まで返品条件を確認する習慣が重要です。
その他クーリングオフが適用されない条件(3,000円未満の現金取引など)
適用される取引類型に該当していても、特定の条件下ではクーリングオフができない「適用除外」のケースがあります。
主な適用除外の条件は以下の通りです。
- 3,000円未満の現金取引:訪問販売や電話勧誘販売で、契約したその場で全額を現金で支払った場合。
- 使用・消費した消耗品:化粧品、健康食品、洗剤などで、自分の意思で使ってしまった分。ただし、事業者が「これらは消耗品である」と書面で明確に伝えていない場合は、使用済みでもクーリングオフ可能です。
- 自動車の購入契約
- 事業者として契約した場合(BtoB取引)
- 海外にいる人に対する契約
これらの例外規定を理解しておくことで、より正確にクーリングオフの可否を判断できます。
クーリングオフ期間を過ぎたらどうする?諦める前に確認すべきことと相談先
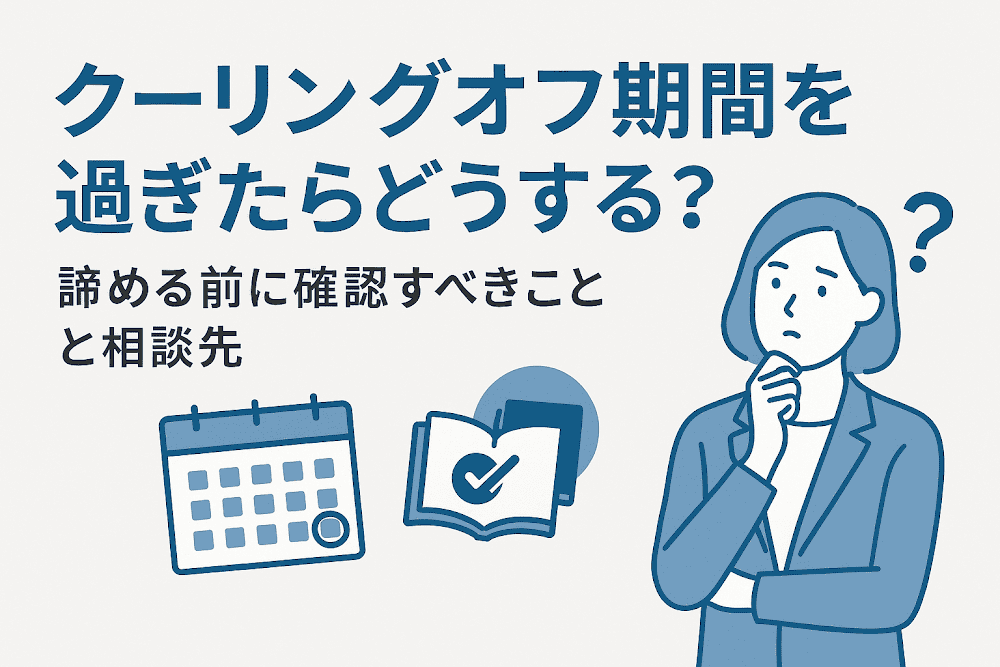
「気づいた時には期間が過ぎていた…」と、落胆してしまうかもしれません。しかし、まだ打つ手がないわけではありません。
期間を過ぎてしまった場合に取るべきアクションは以下の通りです。
- 契約書面を再確認する
- 事業者との交渉や中途解約を検討する
- 専門家である消費生活センターに相談する
すぐに諦めず、冷静にできることを探しましょう。
まずは契約書面を再確認|記載不備なら期間は進行していない可能性
期間が過ぎたと思っても、まずやるべきことは契約書面をもう一度、隅々まで確認することです。
先にも述べた通り、法律で定められたクーリングオフに関する事項が書面に記載されていなかったり、記載方法に不備があったりした場合は、クーリングオフ期間はそもそも始まっていません。また、事業者から「クーリングオフはできない」といった妨害行為があった場合も同様です。
- クーリングオフの告知が赤枠・赤字で書かれているか?
- 文字の大きさは8ポイント以上か?
- 契約内容や金額、事業者名などが正確に記載されているか?
これらの点を確認し、もし不備が見つかれば、期間に関係なくクーリングオフを主張できる可能性があります。
事業者との交渉や中途解約という選択肢
クーリングオフ制度が使えない場合でも、事業者との話し合いによる「合意解約」を目指す道があります。事情を説明し、解約に応じてくれるよう交渉してみましょう。
また、エステティックサロンや学習塾などの「特定継続的役務提供」に該当する契約では、クーリングオフ期間が過ぎた後でも、理由を問わず将来に向かって契約を解除できる「中途解約」の権利が法律で認められています。
ただし、中途解約の場合は、事業者が請求できる損害賠償額の上限が定められており、一定の解約料が発生する可能性があります。それでも、契約を継続して全額を支払うよりは、損害を最小限に抑えられます。
どうしても解決しない場合は消費者ホットライン「188」へ相談
事業者との交渉がうまくいかない、手続きに不安がある、そもそも自分のケースがどうなるのかわからない。そんな時は、一人で抱え込まずに専門家に相談するのが最善の策です。
全国どこからでも利用できる消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話をしましょう。
「188」に電話をかけると、専門の相談員がいる最寄りの消費生活センターや自治体の相談窓口を案内してくれます。相談は無料で、契約内容を伝えれば、クーリングオフが可能か、他にどのような解決策があるかなど、具体的なアドバイスをもらえます。
必要であれば、事業者との間に入って交渉(あっせん)を行ってくれる場合もあります。少しでも困ったら、ためらわずに「188」に電話してください。
クーリングオフ期間や手続きに関するよくある質問
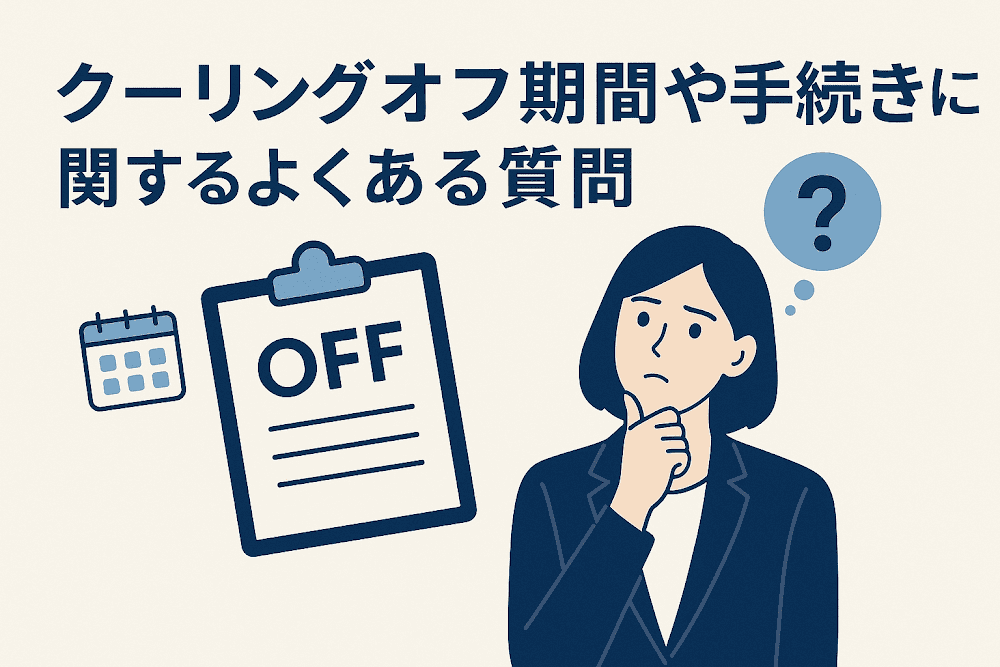
最後に、クーリングオフ制度に関して特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。
クーリングオフをすると違約金や損害賠償を請求されますか?
いいえ、一切請求されません。
クーリングオフは、消費者に無条件で与えられた契約解除の権利です。事業者は、クーリングオフを理由に違約金や損害賠償、商品の使用料などを請求することは法律で固く禁じられています。もし不当な請求を受けても、支払う義務は一切ありません。
商品を開封・使用してしまった場合でもクーリングオフできますか?
原則として可能です。ただし、一部例外があります。
商品を受け取った事業者は、その商品の価値が減っていたとしても、その損失分を消費者に請求することはできません。したがって、開封・使用していてもクーリングオフは可能です。
ただし、化粧品や健康食品、履物といった「消耗品」に指定されているもので、かつ事業者がその旨を書面で通知しており、消費者が自らの意思で使用した分については、クーリングオフの対象外となります。
商品を返送する際の送料は誰が負担しますか?
事業者が負担します。
クーリングオフに伴う商品の引き取りや返送にかかる費用は、すべて販売業者が負担しなければならないと法律で定められています。したがって、消費者は送料を負担する必要はなく、商品を「着払い」で返送すれば問題ありません。