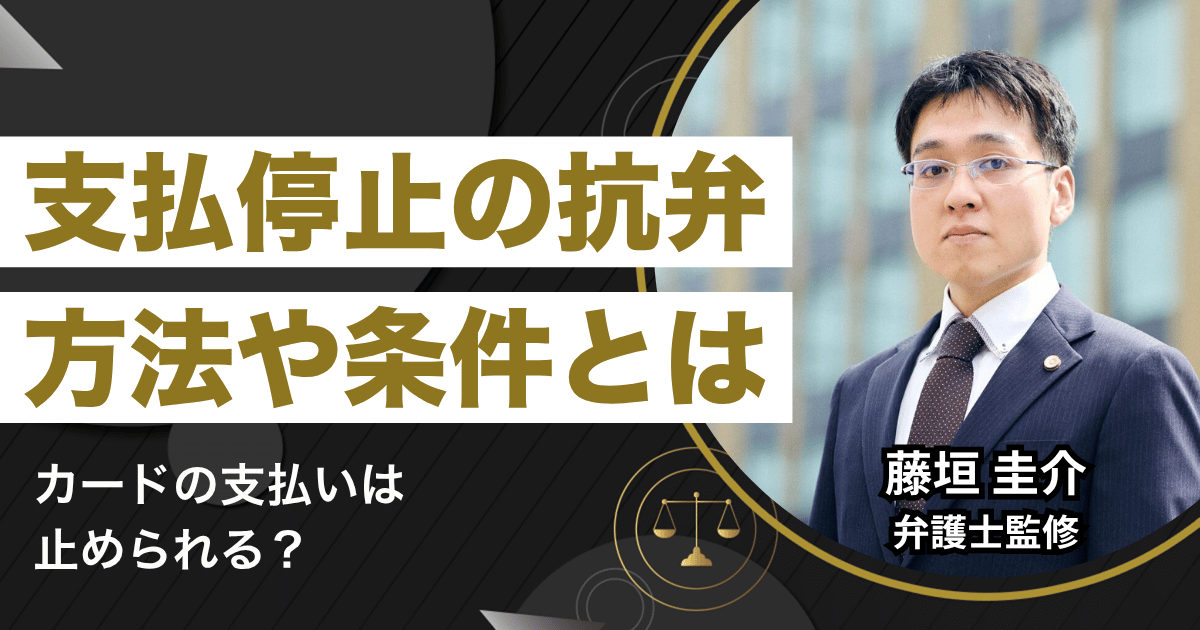「契約したエステが倒産したのに、クレジットカードの支払いだけが続いている」
「高額な情報商材を買ったが、中身が説明と全く違った。業者と連絡も取れない…」
「解約したはずなのに、毎月請求が来る。このまま払い続けるしかないのだろうか…」
このような、販売業者とのトラブルによって生じる理不尽な支払いの悩みを抱えていませんか。泣き寝入りするしかないと諦めかけている方もいるかもしれません。
しかし、諦めるのはまだ早いです。実は、このような状況に陥った消費者を守るための「支払停止の抗弁」という正当な権利があります。
この記事では、クレジットカードの支払いを合法的にストップできる「支払停止の抗弁」について、専門用語を避け、誰にでも分かるように徹底解説します。
この記事を読めば、以下の内容が明確に理解できます。
- 支払停止の抗弁が使える具体的な条件
- 支払いを止めるための手続きの全ステップと、抗弁書の書き方
- 信用情報への影響など、よくある疑問への回答
読了後には、理不尽な支払いに対する不安が解消され、「自分も解決できる」という自信を持って、具体的な行動を起こせるようになっているはずです。
支払停止の抗弁とはクレジットカードの支払いを止める消費者の権利
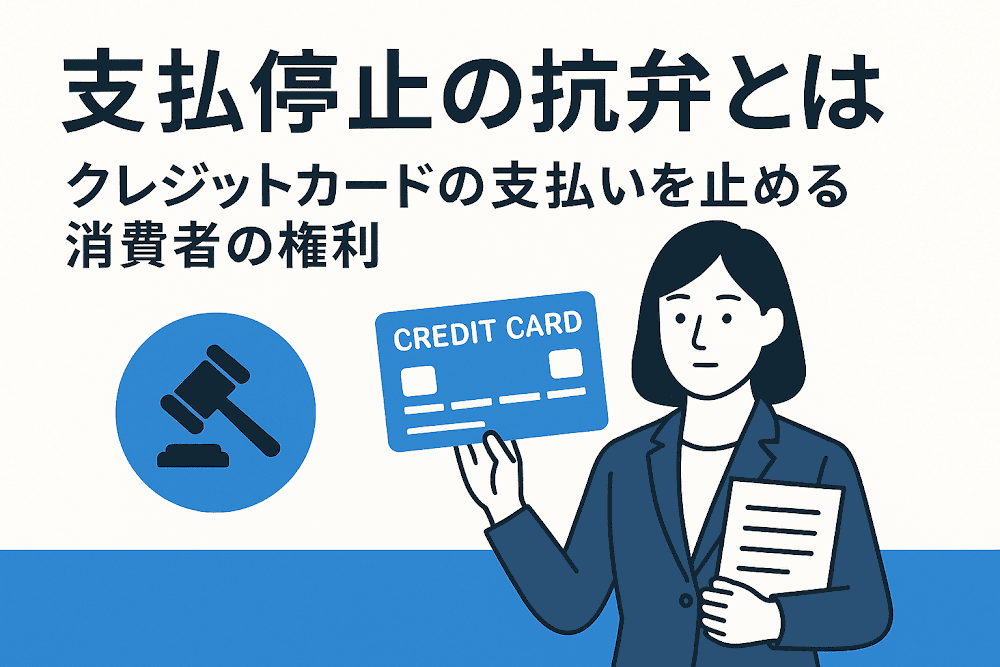
「支払停止の抗弁」とは、一体どのような制度なのでしょうか。この権利の核心は、販売業者との間に起きたトラブルを理由として、クレジットカード会社への支払いを一時的に停止できるという点にあります。
この制度を正しく理解するために、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
- 法律で定められた正当な権利
- 販売店とのトラブルを理由に支払いを一旦保留できる制度
- 契約そのものが無効になるわけではない点に注意
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
支払停止の抗弁は法律で定められた正当な権利
「支払停止の抗弁」は、消費者が勝手に支払いを拒否する行為ではありません。これは、割賦販売法という法律によって明確に定められた、消費者の正当な権利です。この法律は、分割払いやリボ払いといった信用購入あっせんの方法で商品やサービスを購入した消費者が、不利益を被らないように保護することを目的としています。
具体的には、販売業者に対して主張できる理由(商品が届かない、サービスが提供されないなど)があるのであれば、その支払いを代行している信販会社(クレジットカード会社)に対しても、同じ理由で支払いを拒否できる、と定められています。
したがって、この権利を行使することに何ら引け目を感じる必要はありません。法律が認めた、トラブル解決のための強力な武器なのです。
販売店とのトラブルを理由に支払いを一旦保留できる制度
この制度の最も重要なポイントは、「販売店に問題があるから、カード会社への支払いを止めます」と主張できる点にあります。通常、商品の購入契約は「消費者と販売店」の間で、カードの支払い契約は「消費者とカード会社」の間で、それぞれ独立して結ばれています。
しかし、支払停止の抗弁権を行使すると、この2つの別々の契約が連動します。例えば、「エステサロンが倒産してサービスを受けられなくなった」(販売店とのトラブル)という事実を根拠に、「サービスを受けられないのだから、その代金はカード会社にも支払いません」と主張できるのです。
これにより、消費者は、販売業者が倒産したり、連絡が取れなくなったりした場合でも、一方的に支払いを続けるという最悪の事態を避けることができます。あくまで支払いを「一旦保留」する制度ですが、問題が解決するまでの間、金銭的な負担を停止できる非常に有効な手段です。
契約そのものが無効になるわけではない点に注意
支払停止の抗弁は非常に強力な権利ですが、万能ではありません。最も注意すべき点は、この手続きはあくまで「カード会社への支払いを一時的に停止する」だけであり、「販売店との契約そのものを無効にする(なかったことにする)」ものではない、ということです。
つまり、支払いを止めても、販売店との間の契約関係は依然として残っています。もし、販売店側が「契約は有効だ」と主張し、裁判などを起こしてきた場合、それには別途対応する必要があります。
また、この制度は将来の支払いを止めるためのものであり、すでに支払ってしまったお金を取り戻す「返金」の効果はありません。返金を求める場合は、別途、販売店との交渉や、後述する「チャージバック」などの手続きを検討する必要があります。この違いを正しく理解しておくことが重要です。
支払停止の抗弁が使える条件とは?あなたの状況を確認
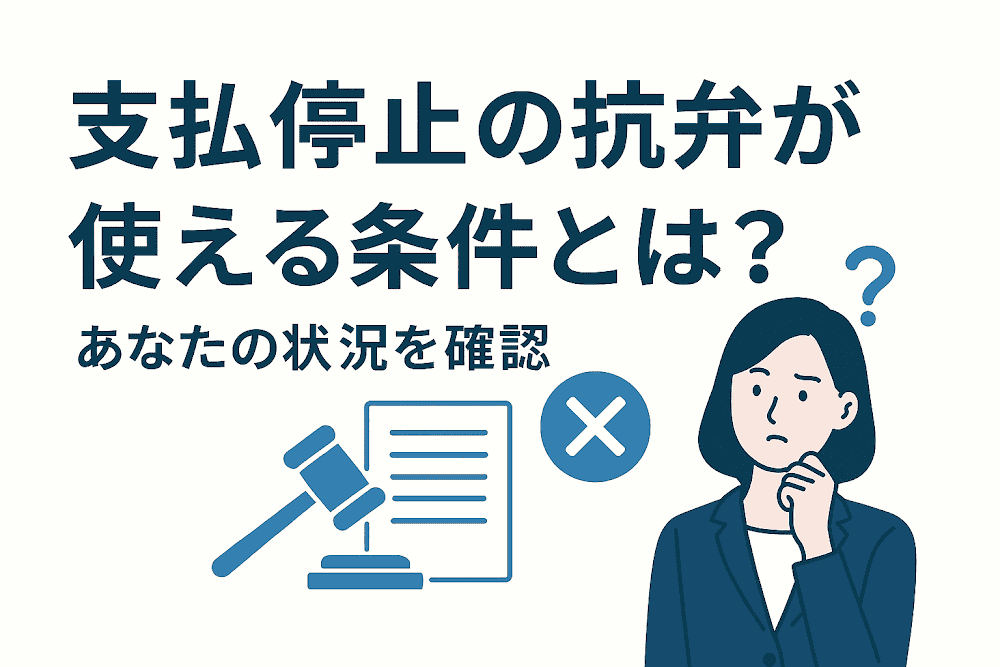
支払停止の抗弁は、どんな場合でも使えるわけではありません。割賦販売法で定められたいくつかの条件をすべて満たす必要があります。ご自身の状況が当てはまるか、以下のチェックリストで確認してみましょう。
- 対象となる支払い方法か?
- 対象となる契約金額か?
- 対象となる理由(抗弁事由)があるか?
- 営業目的の契約ではないか?
これらの条件を一つずつ詳しく解説していきます。
対象となる支払い方法
支払停止の抗弁が利用できるのは、特定の支払い方法に限られています。お使いのクレジットカードの支払い方法が該当するか確認してください。
| 対象となる支払い方法 | 対象外となる支払い方法 |
|---|---|
| 分割払い(3回以上) | 翌月1回払い |
| リボルビング払い(リボ払い) | ボーナス一括払い(※) |
| ボーナス2回払い | 2回払い(※) |
※包括信用購入あっせんの場合を除く
ポイントは、比較的長期にわたる高額な支払いを想定した制度であるという点です。そのため、1回で支払いが完了する「翌月1回払い」や、2回の分割払いは多くの場合対象外となります。クレジットカードの利用明細を見て、ご自身の支払い方法が「分割払い」や「リボ払い」になっているかを確認しましょう。
対象となる契約金額
支払い方法に加えて、契約した商品やサービスの金額にも条件があります。この条件は、支払い方法によって異なります。
- リボルビング払い(リボ払い)の場合
- 現金販売価格(商品の値段)が合計3万8千円以上
- 分割払いなどの場合
- 支払総額(商品代金+手数料)が合計4万円以上
例えば、リボ払いで2万円の商品を購入した場合は対象外ですが、2万円の商品と3万円の商品を同じリボ払いで購入し、合計が5万円になっていれば対象となります。分割払いの場合は、分割手数料を含めた総支払額が4万円以上であることが必要です。契約書や利用明細で、支払うべき総額がいくらになっているかを確認してください。
対象となる理由(抗弁事由)
支払いを停止するためには、その根拠となる正当な理由、すなわち「抗弁事由」が必要です。これは、販売業者側に何らかの問題があることを指します。法律では、以下のようなケースが抗弁事由として例示されています。
商品が届かない・サービスが提供されない(エステの倒産など)
契約したにもかかわらず、約束の商品がいつまでも配送されなかったり、予約していたエステや語学教室が倒産してしまってサービスを受けられなくなったりするケースです。これは最も典型的で、認められやすい理由の一つです。
商品が不良品・見本と違う
届いた商品がすぐに壊れてしまった、広告や見本で見たものと色や性能が全く違う、といったケースです。販売業者が約束した品質や内容を提供していない(債務不履行)と主張できます。
その他、販売店に問題があるケース
上記以外にも、「偽ブランド品だった」「強引な勧誘で契約させられた」「解約したのに請求が続く」など、販売店の契約内容や販売方法に問題がある場合も抗弁事由に該当する可能性があります。重要なのは、その問題点を客観的に説明できるかどうかです。
営業目的・事業目的の契約は対象外
支払停止の抗弁は、あくまで一般の「消費者」を保護するための制度です。そのため、個人事業主が事業のために購入したパソコンや、会社が営業車を購入した場合など、営業目的・事業目的での契約は対象外となります。
この判断は、契約の名義だけでなく、実質的に事業のために利用されるかどうかで決まります。個人的な利用目的で購入したものであることが、この権利を行使するための大前提となりますのでご注意ください。
支払停止の抗弁を行う手続きと流れを4ステップで解説
支払停止の抗弁が使える条件を満たしていることが確認できたら、次はいよいよ実際の手続きに進みます。手続きは、以下の4つのステップで進めるのが一般的です。
- ステップ1:まずは販売店との交渉を試みる
- ステップ2:内容証明郵便で「支払停止の抗弁書」をカード会社へ送付
- ステップ3:カード会社による調査の開始
- ステップ4:調査結果の通知と支払い停止の決定
正しい手順を踏むことが、スムーズな解決への近道です。各ステップで何をすべきか、具体的に見ていきましょう。
ステップ1:まずは販売店との交渉を試みる
いきなりカード会社に連絡するのではなく、まずは問題の原因である販売店に対して、トラブルの解決を求めることが重要です。電話やメール、書面などで「商品が届かないので届けてほしい」「不良品なので交換してほしい」「契約を解約したい」といった要求を明確に伝えましょう。
この段階で問題が解決すれば、支払停止の抗弁を行う必要はありません。また、もし販売店が対応しなかったり、倒産して連絡が取れなかったりした場合でも、「販売店に解決を求めたが、応じてもらえなかった」という事実そのものが、後のステップでカード会社に事情を説明する際の重要な根拠となります。
販売店とのやり取りは、いつ、誰が、どのような内容を話したか、できるだけ詳しく記録に残しておくことを強くお勧めします。
ステップ2:内容証明郵便で「支払停止の抗弁書」をカード会社へ送付
販売店との交渉で問題が解決しない場合、次のステップとして、クレジットカード会社に対して「支払停止の抗弁」を正式に行います。この意思表示は、「支払停止の抗弁に関する申出書(抗弁書)」という書面を提出して行います。
この書面は、普通郵便ではなく「内容証明郵便」で送付するのが最も確実です。内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に差し出されたかを日本郵便が証明してくれるサービスです。これにより、「カード会社に正式に通知した」という動かぬ証拠を残すことができ、「そんな書類は受け取っていない」といった後のトラブルを防ぐことができます。
抗弁書の書式はカード会社によって用意されている場合もありますが、自分で作成することも可能です。次の章でテンプレートと書き方を詳しく解説します。
ステップ3:カード会社による調査の開始
カード会社が支払停止の抗弁書を受理すると、その内容に基づいて調査を開始します。カード会社は、中立的な立場で、契約者(あなた)と販売店の双方から事情を聞き取り、提出された資料などを精査します。
契約者に対しては、トラブルの詳細について電話でヒアリングがあったり、追加の資料提出を求められたりすることがあります。販売店が倒産している場合は、その事実確認などが行われます。
この調査期間中、カード会社は通常、当該契約に関する支払いの請求を一時的にストップします。ただし、これはカード会社の任意の対応であり、法律上の義務ではありません。もし調査期間中も請求が続く場合は、カード会社にその旨を伝え、対応を求めましょう。
ステップ4:調査結果の通知と支払い停止の決定
カード会社は調査を終えると、抗弁を認めるかどうかの判断を下し、その結果を書面で通知してきます。
抗弁が正当なものとして認められれば、正式に支払いの停止が決定します。これにより、問題となっている契約に関する今後の支払いは、問題が解決するまでの間、行う必要がなくなります。
もし抗弁が認められなかった場合は、その理由が書面に記載されています。理由に納得がいかない場合は、消費生活センターなどの専門機関に相談することをお勧めします。理由が「資料不足」などであれば、追加の資料を提出して再度の調査を依頼することも可能です。
【テンプレート付】支払停止の抗弁書の書き方を具体的に解説
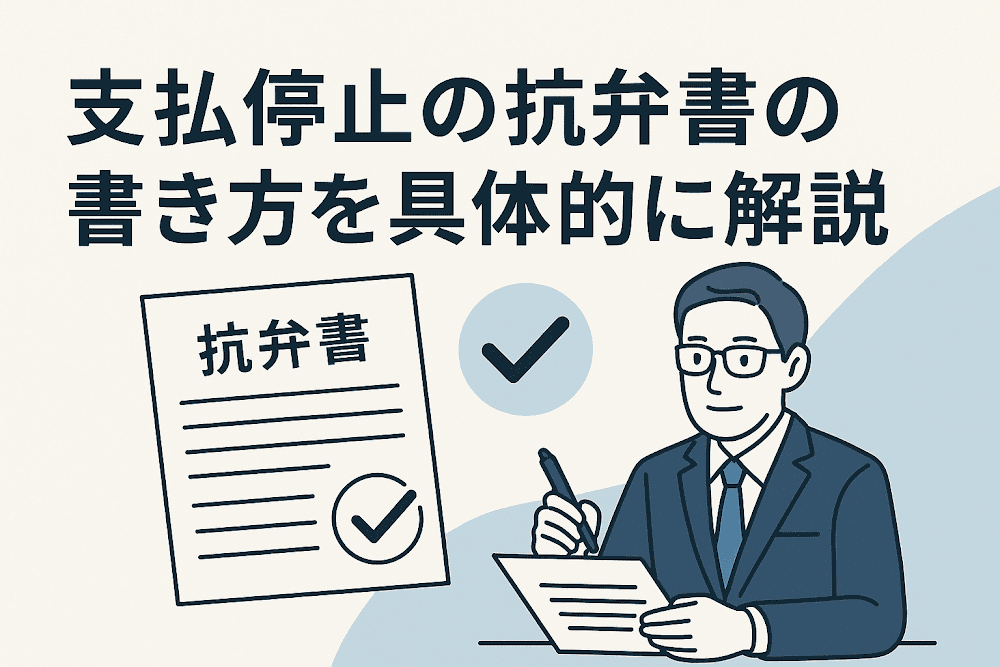
支払停止の抗弁手続きの核心となるのが「支払停止の抗弁書」の作成です。ここでは、誰でも作成できるよう、テンプレート(雛形)と具体的な書き方を解説します。カード会社によっては独自の書式を用意している場合もあるため、事前にカード会社のウェブサイトを確認するか、電話で問い合わせてみるとよいでしょう。
抗弁書のテンプレート(雛形)
以下は、一般的な抗弁書のテンプレートです。ご自身の状況に合わせて内容を修正してご使用ください。
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇(クレジットカード会社名)御中
(あなたの住所)
(あなたの氏名) 印
(電話番号)
(クレジットカード番号)
支払停止の抗弁に関する申出書
私は、貴社との間の下記クレジットカード会員規約に基づき、以下の販売店との契約について、割賦販売法第30条の4第1項に基づき、支払いの停止を請求いたします。
記
1.契約年月日
令和〇年〇月〇日
2.商品名(または役務名)
(例:パーソナルトレーニング6ヶ月コース)
3.契約金額
金〇〇〇,〇〇〇円
4.支払方法
リボルビング払い / 分割払い(〇回)
5.販売店情報
販売店名:株式会社△△
所在地:東京都〇〇区〇〇1-2-3
電話番号:03-1234-5678
担当者名:〇〇 〇〇
6.支払停止を求める理由(抗弁事由)
(ここに、トラブルの内容を具体的に、客観的な事実に基づいて記載します。下記の記入例を参考にしてください。)
7.販売店への請求状況
(ここに、販売店に対してどのような要求をしたか、その結果どうなったかを記載します。)
以上
項目別の書き方と記入例
各項目について、どのように書けばよいか具体的に解説します。
契約者情報・契約内容の書き方
あなたの氏名、住所、電話番号、そして対象となるクレジットカードの番号を正確に記入します。契約内容については、契約書や利用明細を確認しながら、契約日、商品名、契約金額、支払方法をそのまま書き写してください。情報が不正確だと、カード会社での特定に時間がかかってしまう可能性があります。
支払停止を求める理由(抗弁事由)の書き方
ここが最も重要な部分です。感情的にならず、「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように」という5W1Hを意識して、起きた事実を時系列で客観的に書きましょう。
【記入例:エステが倒産した場合】
令和〇年〇月〇日、上記販売店にてパーソナルトレーニング6ヶ月コース(全24回)の契約を締結しました。しかし、令和〇年〇月〇日に販売店の店舗を訪れたところ、「破産手続開始のお知らせ」という貼紙があり、営業を停止していました。電話も繋がらず、担当者とも連絡が取れない状況です。契約24回のうち、まだ18回分のサービスが提供されておらず、これは販売店の債務不履行に該当するため、残りの支払いを停止するよう求めます。
販売店への請求状況の書き方
ステップ1で行った販売店との交渉内容を記載します。
【記入例】
令和〇年〇月〇日、販売店のウェブサイトに記載のあった連絡先に電話をしましたが、繋がりませんでした。また、同日、問い合わせフォームからも連絡を試みましたが、現在に至るまで返信はありません。
書類作成時の注意点と送付方法
抗弁書を作成する際には、以下の点に注意してください。
- 証拠のコピーを添付する: 契約書、パンフレット、保証書、販売店とのメールのやり取りなど、主張を裏付ける証拠があれば、そのコピーを同封しましょう。トラブルの状況がより明確に伝わります。
- 原本は手元に保管する: カード会社に送るのは必ずコピーにし、契約書などの原本はご自身で大切に保管してください。
- 内容証明郵便で送付する: 前述の通り、郵便局の窓口で「内容証明郵便でお願いします」と伝えて送付します。同じ内容のものを3部(自分用、カード会社用、郵便局保管用)用意する必要があります。
※内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間受付を行っているe内容証明(電子内容証明)を使用することも可能です。
支払停止の抗弁に関するよくある質問
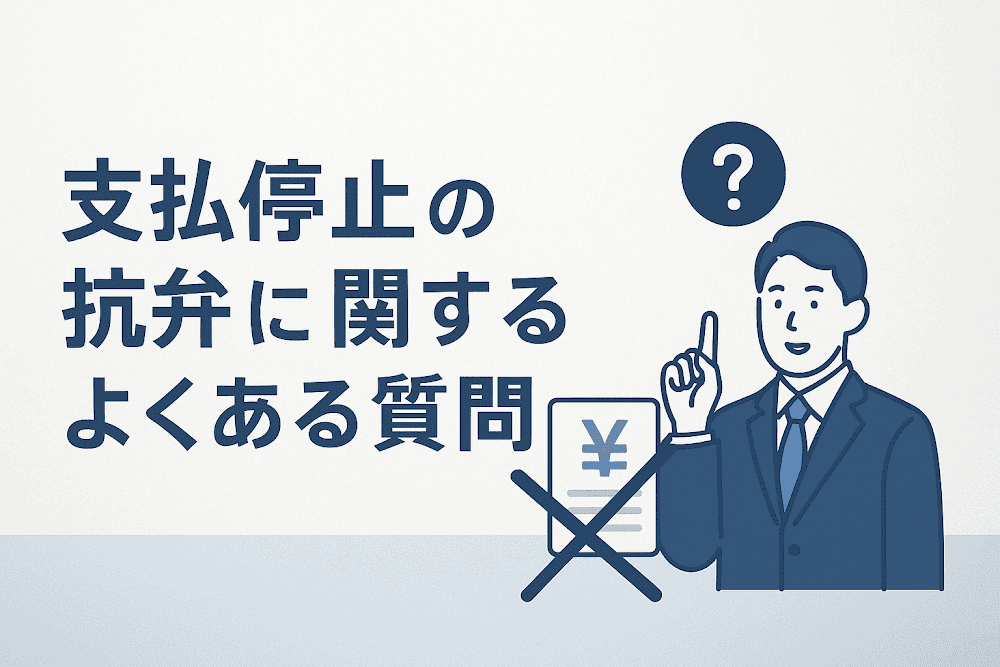
支払停止の抗弁を検討する際、多くの方が疑問や不安に思う点があります。ここでは、特に多い質問とその回答をまとめました。
信用情報(ブラックリスト)に傷はつきますか?
最も心配されるのがこの点ですが、結論から言うと、支払停止の抗弁を正当な理由に基づいて行った場合、信用情報に傷がつく(いわゆるブラックリストに載る)ことはありません。
信用情報機関に延滞情報として登録されるのは、正当な理由なく支払いを遅らせた場合です。支払停止の抗弁は、割賦販売法という法律に基づいて支払いを停止する正当な権利の行使であり、単なる「支払い遅れ」や「延滞」とは全く性質が異なります。
そのため、カード会社もこの手続きを延滞として処理することはありません。内閣府の調査報告書でも、この権利の重要性が指摘されており、安心して手続きを進めてください。
すでに支払ったお金は返金されますか?
残念ながら、支払停止の抗弁の手続き自体に、すでに支払ったお金を取り戻す(返金する)効果はありません。この制度は、あくまで「これから先の支払いを止める」ためのものです。
返金を求める場合は、別途、販売店に対して交渉する必要があります。しかし、販売店が倒産していたり、交渉に応じなかったりすることも少なくありません。
その場合の代替策として、「チャージバック」という制度があります。これは、カード会社が販売店に代金の支払いを拒否したり、一度支払った代金を取り戻したりするルールで、カード会社の判断で返金処理が行われる場合があります。支払停止の抗弁とあわせて、カード会社に相談してみるとよいでしょう。
カード会社に拒否されることはありますか?
はい、支払停止の抗弁が認められないケースもあります。カード会社に拒否される主な理由は以下の通りです。
- そもそも抗弁の条件を満たしていない: 支払い方法が翌月1回払いだったり、契約金額が条件に満たなかったりする場合です。
- 抗弁事由が客観的に認められない: 「商品がなんとなく気に入らない」といった主観的な理由や、主張を裏付ける証拠が乏しい場合、抗弁は認められにくい傾向にあります。
- 販売店側の主張が正当だと判断された場合: 例えば、「商品の不具合は消費者の使い方が原因である」と販売店側が証明した場合などです。
カード会社はあくまで中立の立場で調査を行うため、支払いを停止するだけの客観的で正当な理由があることを、書類や証拠で示すことが非常に重要になります。
手続きに弁護士は必要ですか?費用はかかりますか?
支払停止の抗弁の手続きは、基本的にご自身で行うことができ、弁護士に依頼する必要は必ずしもありません。また、手続き自体に手数料などの費用はかかりません。内容証明郵便の料金(通常1,500円~2,000円程度)が実費としてかかるくらいです。
この記事で解説した手順や書き方を参考にすれば、ほとんどのケースでご自身での対応が可能です。
ただし、販売店とのトラブルが非常に複雑で、損害賠償請求なども含めて法的な対応を検討している場合や、カード会社との交渉がうまくいかない場合には、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談することも有効な選択肢となります。
支払停止の抗弁が使えない場合の他の解決策
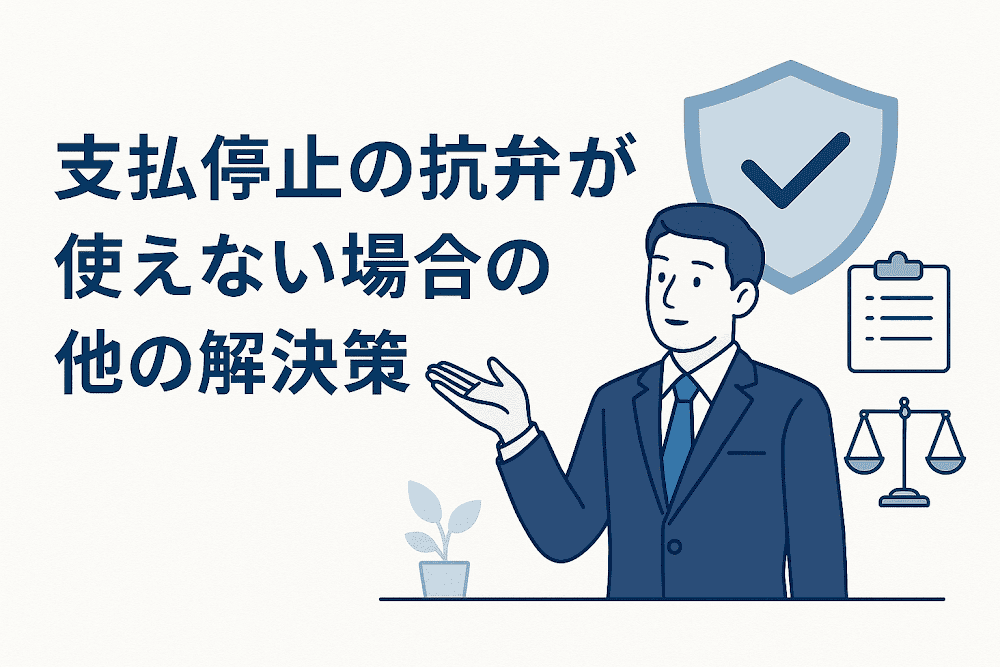
ご自身の状況が支払停止の抗弁の条件に合わなかったり、抗弁が認められなかったりした場合でも、諦める必要はありません。他にも消費者を守るための制度があります。
クーリング・オフ制度との違いと使い分け
クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売など、特定の取引方法で契約した場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
支払停止の抗弁との大きな違いは、「契約そのものを白紙に戻せる」点と、「理由を問われない」点です。一方で、適用できる取引方法や期間(原則8日間または20日間)が厳しく定められています。
契約してから日が浅く、クーリング・オフの対象となる取引であれば、まずはこちらの利用を検討するのがよいでしょう。期間が過ぎてしまった場合に、支払停止の抗弁を検討するという流れになります。
契約の取消・無効を主張する方法
販売店の勧誘方法に問題があった場合、消費者契約法などに基づいて契約の「取消」や「無効」を主張できる可能性があります。
例えば、「絶対に儲かる」といった事実と異なる説明(不実告知)をされて契約した場合や、「今日中に契約しないと大変なことになる」と不安を煽られて契約した場合(困惑)などが該当します。
契約の取消が認められれば、契約は初めからなかったことになり、支払ったお金の返還を請求できます。支払停止の抗弁よりも根本的な解決を目指す方法ですが、法的な主張が必要になるため、消費生活センターや弁護士への相談が推奨されます。
チャージバック(カード会社の返金ルール)とは
チャージバックは、法律で定められた制度ではなく、VISAやMastercardなどの国際カードブランドが定めるルールに基づく救済措置です。カード会員が正当な理由なく不利益を被った場合に、カード会社がその売上を取り消し、消費者に返金を行う手続きを指します。
「商品が届かない」「注文と違う商品が届いた」「二重請求された」といったケースで利用できる可能性があります。支払停止の抗弁が「支払いを止める」制度であるのに対し、チャージバックは「返金を求める」制度である点が異なります。
申請できる期間や条件はカード会社によって異なるため、利用したい場合はまずカード会社に相談してみましょう。
【事例別】支払停止の抗弁でクレジットカードの支払いを止めたケース
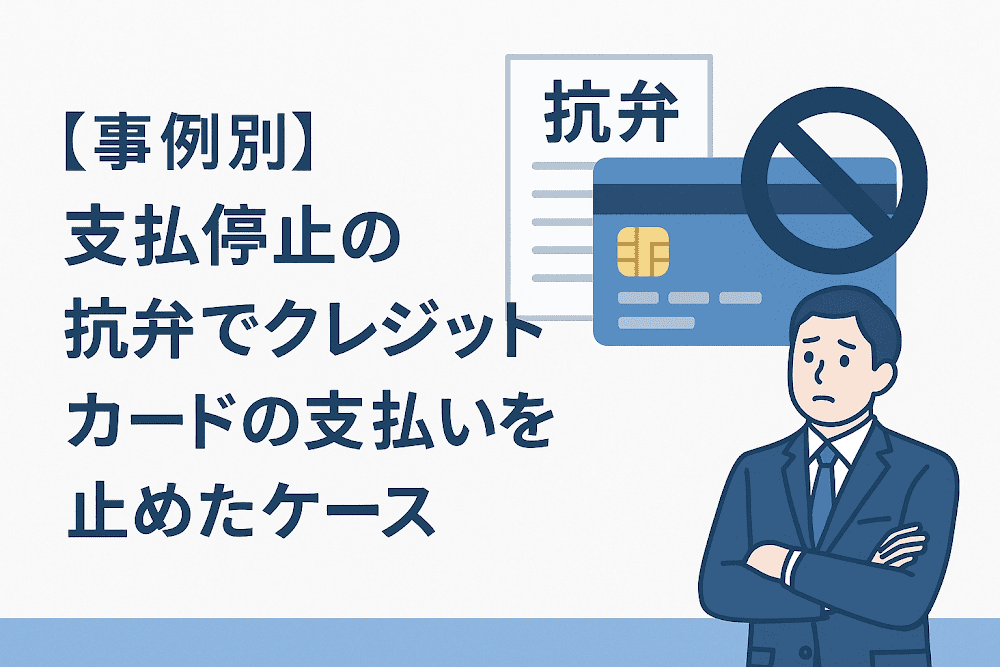
支払停止の抗弁が、実際にどのような場面で役立つのか、具体的な事例を通じて見ていきましょう。ご自身の状況と似たケースがあれば、解決へのイメージが湧きやすくなるはずです。
事例1:契約していたエステサロンが倒産した
Aさんは、半年前にあるエステサロンで20万円の痩身コース(1年間・全12回)を契約し、クレジットカードの分割払い(12回)で支払っていました。これまで4回通いましたが、ある日サロンに行くと「破産のため閉鎖します」という貼紙が。販売店とは一切連絡が取れなくなってしまいました。
Aさんは、まずカード会社に連絡。支払停止の抗弁を行いたい旨を伝え、抗弁書を送付しました。抗弁書には、契約内容と、サロンが倒産して残りの8回分のサービスが受けられなくなった事実を具体的に記載。その結果、カード会社の調査を経て抗弁が認められ、残りの支払いをすべて停止することができました。このようなエステの倒産事例は、国民生活センターにも多く寄せられています。
事例2:購入した高額な情報商材が詐欺だった
Bさんは、「誰でも簡単に月50万円稼げる」という謳い文句のオンライン広告を見て、30万円の情報商材をクレジットカードのリボ払いで購入しました。しかし、送られてきた教材の内容は、インターネットで誰もが無料で調べられるような情報ばかりで、到底稼げるようなものではありませんでした。
販売店に返金を求めても「情報という商品の性質上、返金には応じられない」の一点張り。そこでBさんは、消費生活センターに相談の上、カード会社に支払停止の抗弁を行いました。「広告内容と実際の商品内容が著しく異なる(品質の問題)」ことを理由に、具体的な相違点を抗弁書に記載。カード会社の調査の結果、Bさんの主張が認められ、今後のリボ払いの支払いを停止できました。近年、このような情報商材に関する相談は増加傾向にあります。
事例3:解約したはずのオンラインサービスの請求が続く
Cさんは、月額5,000円の動画編集ソフトの年間プランを契約していましたが、使わなくなったため、正規の手順に従ってウェブサイトから解約手続きを行いました。解約完了のメールも受信して保管していました。
しかし、その後も毎月クレジットカードから5,000円が引き落とされ続けています。販売店のサポートに何度も連絡しましたが、「解約処理が確認できない」と言われ、対応してもらえません。
そこでCさんは、カード会社に支払停止の抗弁を申し出ました。「解約済みであるにもかかわらず請求が続く」という販売店の契約不履行を理由とし、証拠として解約完了メールのコピーを提出。カード会社はCさんの主張を認め、不正な請求の支払いを停止しました。
一人で解決が難しいときは公的な専門窓口へ相談を
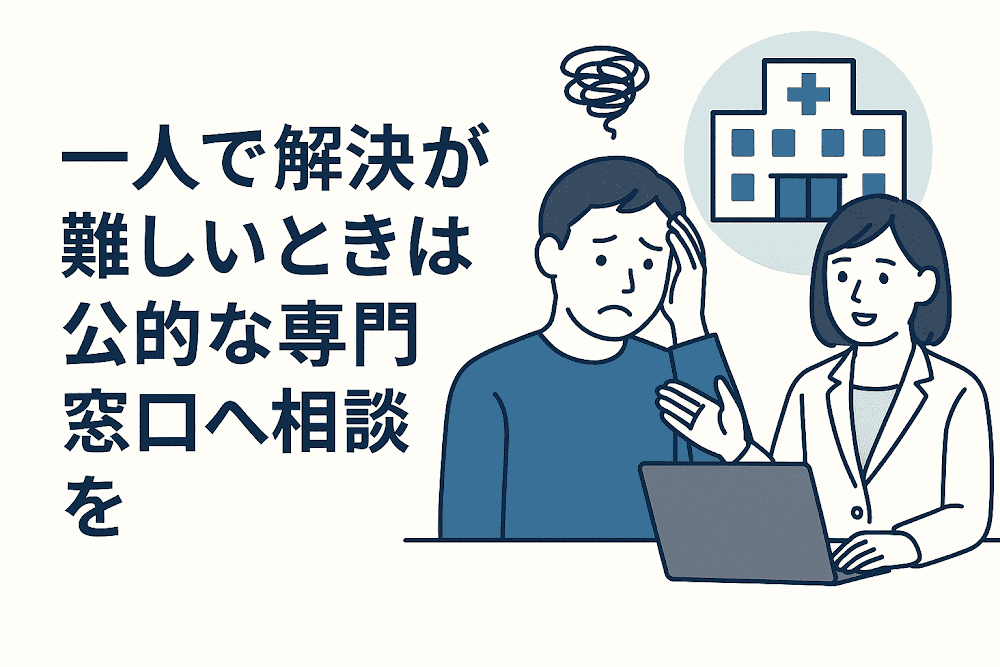
支払停止の抗弁はご自身で手続き可能ですが、「自分のケースで使えるか判断が難しい」「抗弁書の書き方が分からない」「カード会社に拒否されてしまった」など、困ったときや不安なときは、一人で悩まずに専門の相談窓口を利用しましょう。無料で相談できる、信頼性の高い公的な窓口があります。
全国の消費生活センター(消費者ホットライン188)
消費生活センターは、商品やサービスの契約に関するトラブルなど、消費生活全般に関する相談を受け付けている公的な機関です。支払停止の抗弁についても専門的な知識を持っており、手続きの方法や書類の書き方について具体的なアドバイスをもらえます。
どこに相談してよいか分からない場合は、まずここに電話してみましょう。局番なしの「188(いやや!)」に電話をかけると、最寄りの相談窓口を案内してくれます。中立的な立場で、問題解決のための最善の方法を一緒に考えてくれる、心強い味方です。
日本クレジット協会の相談窓口
一般社団法人日本クレジット協会は、クレジット業界の自主規制機関であり、消費者からの相談を受け付ける「消費者相談室」を設けています。クレジットカードに関するトラブルに特化しているため、より専門的なアドバイスが期待できます。
「カード会社との交渉がうまくいかない」「カード会社の対応に納得できない」といった場合に相談すると、業界のルールや慣行に基づいた助言を得られる可能性があります。ウェブサイトから相談内容の詳細を確認し、電話で問い合わせてみてください。